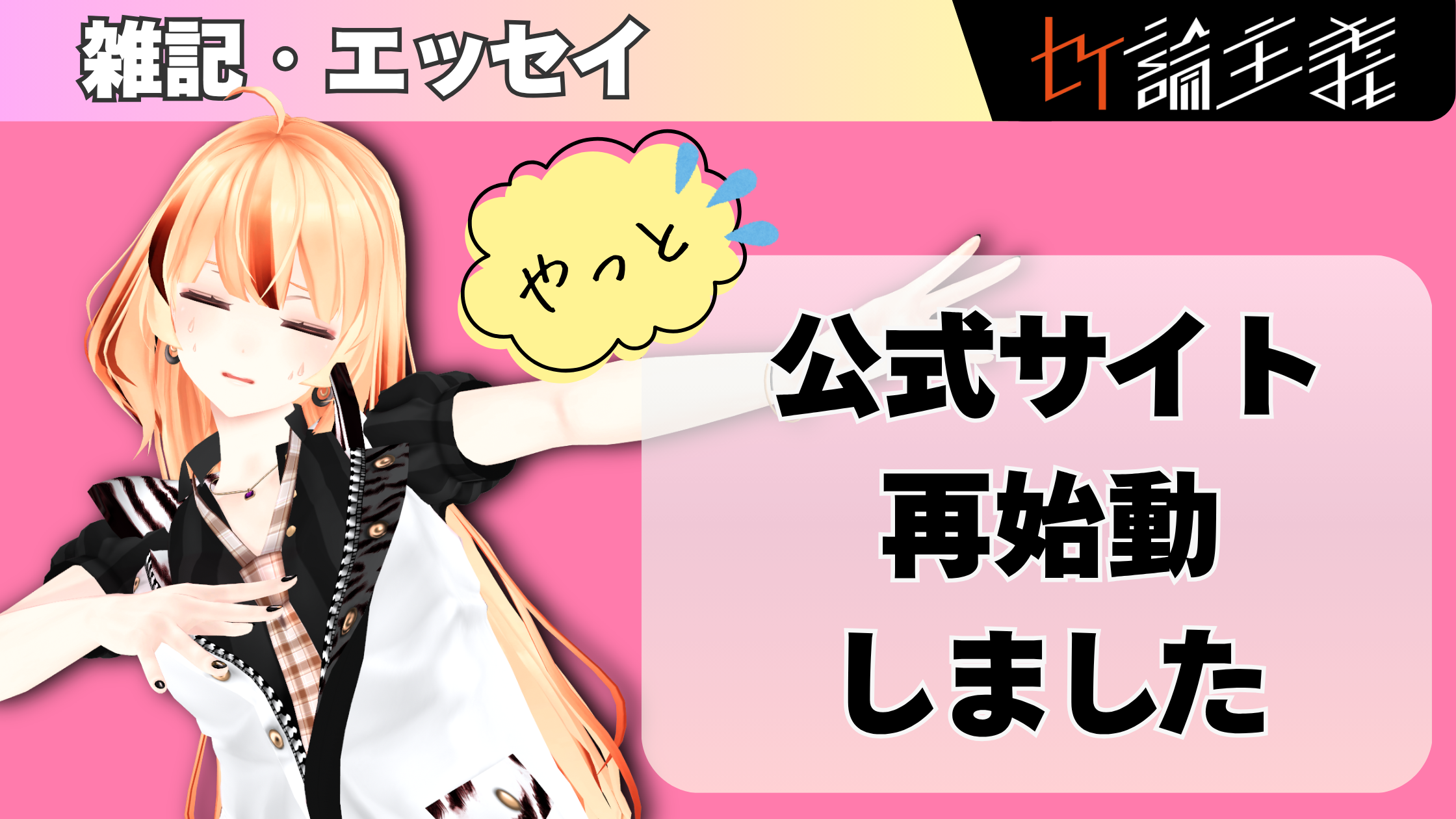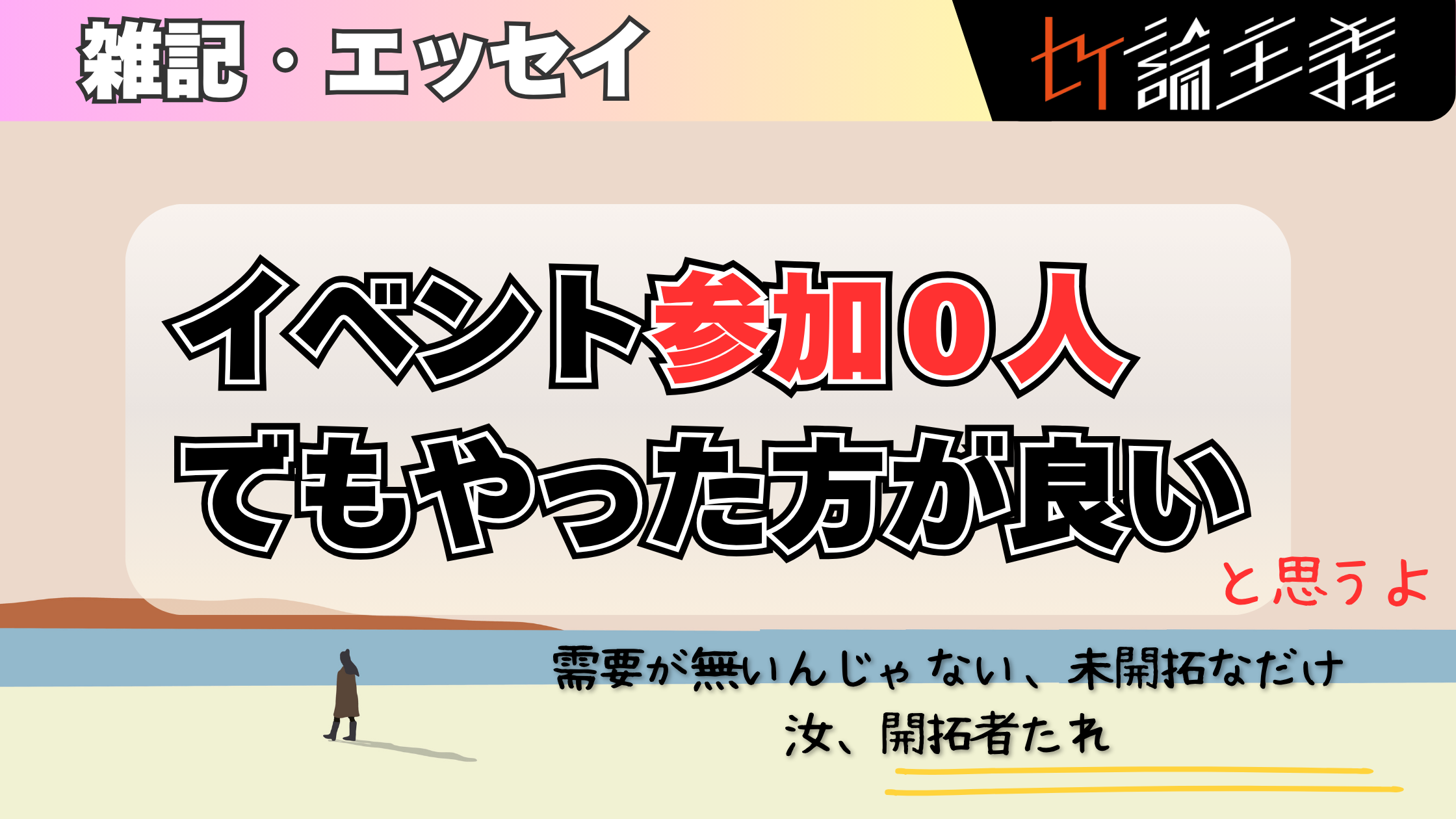【読書感想】あの人の調べ方ときどき書棚探訪|感想とおすすめしたい理由

最近本を読んでないなぁと思ったので、本屋さんで目に付いた本を読んでみることにしました。
今回は笠間書院から発売されている、平山亜佐子さんの『あの人の調べ方ときどき書棚探訪 クリエイター20人に聞く情報収集・活用術』です。
動画配信プラットフォーム「シラス」で作られた「平山亜佐子のこちらの文献調査局」という番組の文字起こしを本にしたもので、平山さんと20人のクリエイターの対談形式の本になっています。
こちらの本の魅力をざっくり3行で説明すると……
- 正直『調べ方』の参考にはならない。が、面白い本である。
- 熱意や探求心が物凄い方ばかりで、知識量も多い。
- インタビュー本なのに、展開があって面白い。
では、それぞれに関して解説していきたいと思います。
①正直『調べ方』の参考にはならない。
『調べ方』の参考にはならない。
という書き方をしてしまいましたが、これを読んで実際に実行すれば、調べものには困らないでしょう。(実行できるものなら、という意味です)
本作に出てくる方々は調べものに関して熱意が凄くて、「〇〇について調べたいから、〇〇の原点が記載されているらしい本を探す」とか「〇〇が記載されていそうな本を片っ端から取り寄せて読む」とか「〇〇の情報が不確定だから、色々な資料を読み漁る」とか……
簡単に言うと、’力業’で調べものをしているなぁ、という印象が強かったです。
そのため、〇〇についての革新的な調べ方とか楽に調べる方法……なんてものはあまりありません。逆に、情報というものを精査したり調べたりするには、やはり地道で労力が掛かる作業が必要なんだなぁ……と思わせてきます。
本作の魅力は『調べ方』ではなく、別の部分にあります。
②熱意や探求心が物凄い方ばかりで、知識量も多い。
本作のインタビュー相手として起用されるくらいのクリエイターの方々なので、誰をとっても何かに対して物凄い熱意のある人が多いです。
着目する分野はバラバラですが、ニッチなものだったり、ちょっとアングラ要素を含んだり、気になるものが多かったですね。
個人的には本書で触れられていた『夫人小説大全』は読んでみたいなぁと思いました。
(調べてみたらWEB連載なんですね、リンク先から読めます)
あとは、『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』とか、SM・SFに関連する書籍は読んでみたい! と思いました。
本作1冊読むだけで少なくとも10冊は気になる本が出来る、そういう本です。
③インタビュー本なのに、展開があって面白い。
これは意図しているところか不明ですが、クリエイターの対談の文字起こしだけかと思いきや、本の展開としてもかなり面白いと感じました。
①で書いたように、力業的な調べ方で片っ端から資料を探す方が出る一方、そういった手法が及ばない分野が出てきます。
エロです。
本作ではアダルトメディア研究家の方もインタビューされています。
そして、昔から調べものをされてる方ばかりなのかなぁ?
と思って読み進めると、『はいよろこんで』のMVを作られた、かねひさ和哉さんのインタビューが出てきたり。
かねひささんは昭和風のアニメーションを作られていますが、とてもお若いそうで、若い方の目線が見れたり。
ただただインタビューを文字起こししただけではなく「次はこう来るか」という展開が楽しめる本でした。
(そもそもの動画を作られた際、幅広い分野からお呼びされたんでしょうね)
ざっくりまとめ
- 正直『調べ方』の参考にはならない。が、面白い本である。
→なぜなら、凄すぎる人が多いから - 熱意や探求心が物凄い方ばかりで、知識量も多い。
→凄すぎるゆえに雑談も豊富 - インタビュー本なのに、展開があって面白い。
→色々な分野の方のインタビューが聞けるし飽きない
今回は笠間書院から発売されている、平山亜佐子さんの『あの人の調べ方ときどき書棚探訪 クリエイター20人に聞く情報収集・活用術』レビューでした。
レビューの本筋に関係ない話
『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』の作者の済東鉄腸さんは、英語で現地の方とコミュニケーションを取っているようで、日本から見てマイナー言語でマイナー映画扱いされているジャンルはやっぱり英語が出来ないと現地の人と話せないのか……と思いました。
というのも、私はインド映画が好きで、日本では若干持ち上げられつつもまだマイナー。そして、現地の人から見た俳優さんとか、現地の人から見た映画の感想とかも知りたいなぁと思っているのですが、英語がまったくダメなので、コミュニケーションを取るのが難しい。
英語が苦手だし、将来は翻訳も自動で出来るようになるし勉強しなくても大丈夫でしょ!と思って怠けていたツケがここに来たのか……。
あとは、本の中で触れられていた、コンビニの漫画の話も懐かしい気分になりました。
漫画の週刊誌のようなちょっと粗い紙質で「人間が怖いホラー特集」みたいなオムニバス形式の漫画本だったり名作の〇〇特集(例えば「こち亀の日暮特集」)みたいな、あるエピソードだけ抜き出した漫画本だったり、そういうのって最近見ないですよね。
入院した時とか、病院の待ち時間とか、長時間の移動前に買って読んでた覚えがあります。
今はやっぱり漫画アプリとかに圧されて無くなっちゃったんでしょうか。
読みたくてメモしてあるのだろうけど、どの話の流れで話題が出たのか忘れてしまった
できる研究者の論文生産術 どうすれば「たくさん」書けるのか
この本も読んでみたいなぁ
吉川浩満さん回では、1冊あたり50MB強の本を1万冊自炊しているという話が出ました。
1冊あたり50MB強だそうです。それを1万冊かぁ……大変そうだなぁと思って読み進めると総データ量は1.6TBとのこと。
バックアップなどサーバーの管理に関しても、金額は拍子抜けするほど安い。
自炊化は業者に頼むと50冊数千円なので、ちょっと高い気もしますが、全体的に「あれ?そんな金額でいけちゃうの?」と思うくらいでした。
その他にもバーチャル書棚の話題だったり。最近発行された本なので、VRの話題に触れられていたりして新鮮でした。