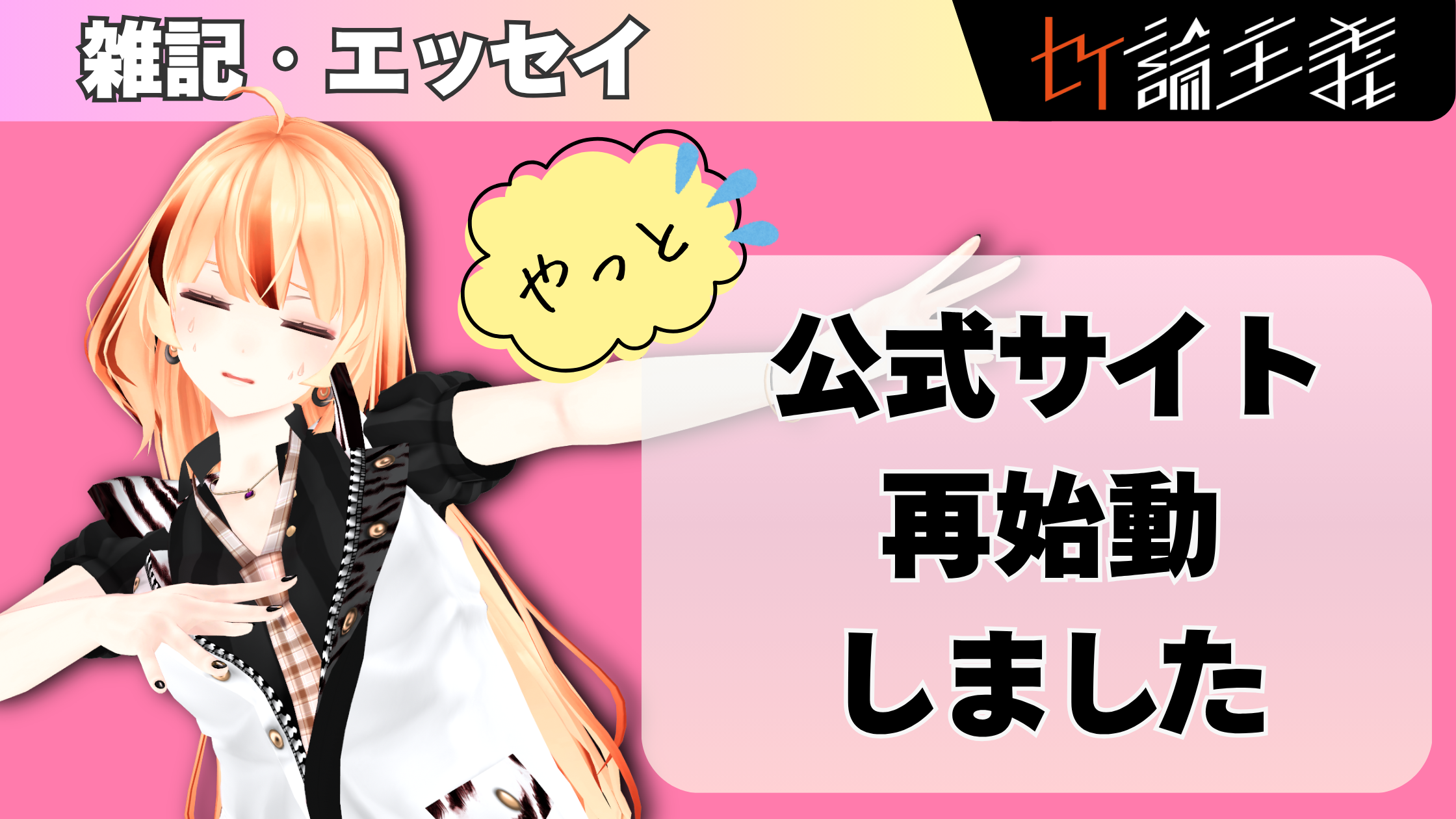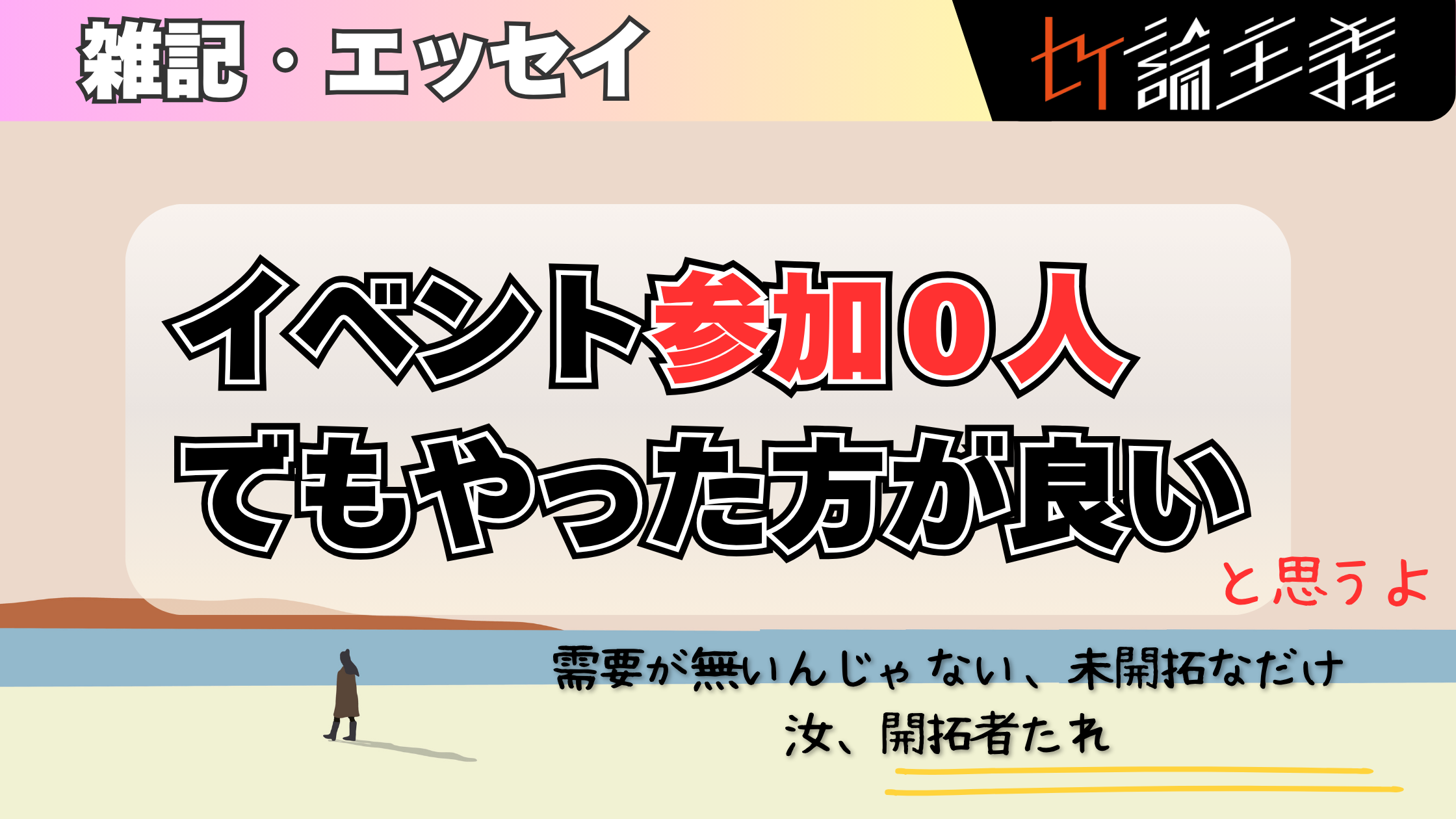clusterのCEOが語るメタバースの未来とは?加藤直人著レビュー
VRChatやclusterで日々メタバースに触れてきた私が、
clusterの運営元・クラスター社のCEOが書いた本を手に取りました。
本書では、メタバースの歴史や現状、今後の可能性が幅広く語られています。
特に「なぜclusterはここまで初心者に優しいのか?」という疑問に対する答えや、
メタバースの“インフラ”を作るという思想に深く共感しました。
はじめに
どうもこんにちは、CHiHAYA(ちはや)と申します。
私は、2018年ごろから、ゆるくメタバースと付き合ってきました。
最初はVRChat。そこからclusterにも触れるようになって、最近は気づいたら両方で過ごす時間がじわじわ増えてきています。
とはいえ、楽しいとか居心地がいいとか、なんか新しい技術でワクワクする!
……そういう感覚をただ受け入れていたというか。
「メタバースってそもそも何?」「何が“革新的”なの?」みたいな、背景や成り立ちについては実は全然知らないまま、数年が過ぎていました。
ちょうどそんなとき、久々に立ち寄った本屋の棚に「メタバース」の文字が並び出し、そしてだんだんと増えてきているのを見かけて、少し気になりました。
そういえば、自分の遊んでいる“この世界”の背景って、何も知らないな……と。
メタバースという言葉が流行語として浮上したのは2021年ごろかららしいのですが、その中身や歴史は人によって理解もまちまちです。
ならば一度、ちゃんと本を通して知ってみよう、と。
そんな中、clusterで遊んでいるときに、ふと「このサービスって、どんな思いで作られたんだろう?」「何を目指しているんだろう?」という疑問が頭をよぎるようになりました。
ただ“遊ぶ場所”としてだけでなく、その設計思想や運営者の視点をもっと知りたい――そう思って手に取ったのが、クラスター株式会社 代表取締役CEO・加藤直人さんの著書、
『メタバース さよならアトムの時代』です。
clusterという“自分の今いる場所”の運営者本人が、どんな考えでこの世界を作ったのか。
clusterで遊ぶ私たちの事については、どう思っているのかなぁ。
あとは、clusterで遊ぶうちに感じる違和感……というか、他のサービスと明確に違うなぁ、なぜこのような展開をしているんだろうと思った点がいくつかあったので、その疑問の答えが書いてあると良いなぁと思いました。
この本はどんな人向け?
私は「クラスター株式会社の代表が書いた本を読んでみたい」という、ちょっとピンポイントな動機でこの本を手に取りました。
なので正直、内容のど真ん中で語られている“メタバースの歴史や定義、今後の社会像”といった部分については、読みながら「なるほどなぁ、ふーん」と雑学的に知識を取り入れただけという感じです。
本の構成としては、
- メタバースとは何か?
- AR・VR・XRといった技術の違い
- どんな歴史をたどってきたか?
- どの企業が何をしてきたのか?
- そしてこれから社会がどう変わるか?
といった情報が丁寧に整理されていて、メタバースにこれから関心を持つ人〜ライトユーザー層向けに書かれた、導入的な内容が中心です。
一方で、メタバースにある程度馴染みのある人が読んでも、「視点の整理」や「全体の構造」を把握するにはとても良い本だと思いました。
特に、clusterやVRChatのようなサービスをただ楽しんでいた自分にとっては、これまで見えなかった“歴史の裏側”が見えてくるような感覚がありました。
感想の立場について
ここから書いていく私の感想は、あくまで
「clusterというサービスに強く関心を持っている一個人」の視点に寄っています。
そのため、本の中でも特に「加藤直人さん個人のビジョン」や、「clusterというサービスがどう考えられてきたか」といった部分に自然と焦点が当たってしまっていると思います。
本全体の主軸とは少しズレるかもしれませんが、そうした一つの読み方もあるのだということで、気軽に読んでもらえたらうれしいです。
単なる「感想ブログ」で全部をカバーできるような本ではないので、ぜひ実際に読んでみて、自分なりの気づきを持ってもらえるといいなと思います。
バーチャル経済圏のインフラ
clusterを始めてまず驚いたのが、新規ユーザーや初心者に対するサポートの手厚さ、そしてCreators Guideの充実ぶりでした。
clusterの [Creators Guide(リンク先)] では、ワールド制作やイベント開催を初めて行う方向けに、基礎からわかりやすく解説がされています。
ですが、率直に言って「ここまでやるか!?」と思うレベルでコストがかけられているのです。
普通、メタバースを題材にしたサービスを運営していて、「これから儲けていこう」と考えている企業であれば、ここまでのサポート体制は企業目線で見ると明らかに“過剰”だと感じるでしょう。
cluster独自の仕様があるので、その分の解説が必要なのは理解できます。
しかし、それにしても「これはもう“サービスを広げる”というより、“技術者を育てようとしてるのでは?”」という印象を受けました。
「一般企業が、なぜここまでコストをかけるのか?」というのが、長らく私の疑問でした。
この本の中で、クラスター社が「バーチャル経済圏のインフラを作る」という理念のもとでサービスを展開していることが語られており、「インフラ」という言葉はたびたび登場します。
「インフラ」と聞いて私が真っ先に思い浮かべたのは、公共工事や上下水道の整備といった、“人々の生活を支えるために、利益度外視でも構築が必要なもの”というイメージでした。
メタバースという仮想空間を成立させるためには、現状ではBlenderやUnityといったツールとの連携が不可欠です。
そうした技術的な土台を支える情報や解説にコストをかけるのは、たしかに「インフラ」としての視点を持っているからこそだと感じます。
さらにclusterには「ワールドクラフト」という、アプリ内でワールドを作成できる機能もあります。
これはBlenderやUnityを使わなくても、誰でも簡単にワールドを作れるという意味で、“参入のハードルを下げるインフラ”としても非常に優れていると感じます。
この本を読んだことで、「なぜclusterはここまで手厚いガイドやサポートを提供しているのか?」という、以前から抱いていた疑問が一つ、明確に解消されました。
VRMは手軽で手軽じゃない
本書では、アバタービジネスについての章でVRoidやVRMといった話題にも触れられていました。
※ただ、ここから先はかなり本の話から脱線した部分になります。
まずVRoidについて簡単に説明すると、「初心者でも手軽にアバターを作れるツール」です。
プリセットを選べば、スマホのキャラメイクのような感覚で、何ひとつ難しいことをしなくても顔や衣装を着せ替えることができますし、
少し慣れてくればモンハンのキャラクリのように目や鼻の形を数値で細かく調整したり、自作の服テクスチャを当てたりと、初級者〜中級者にとってとても優秀なアバター作成環境だと思います。
私自身も、VRChatを始めた頃はVRoid製のアバターを使っていました。
clusterでは「REALITY(リアリティ)」という別のバーチャルサービスとの連携もあり、リアリティで作ったアバターをそのままclusterでも使うことができます。
それが可能なのは、どちらのサービスもVRMという共通フォーマットに対応しているからです。
このVRM形式は、今後ますます多くのメタバースサービスで採用されていくと予想されます。
その点で、clusterが「共通フォーマットとしてVRMを選択している」のはインフラとして正しい判断だと感じました。
ただし、実際のユーザー体験として、ここに一つ大きな壁があると私は思っています。
よく話題になるのが、「VRChatのユーザーがclusterになかなか来ない」という話です。
VRM化の壁
私もVRChatのフレンドと話していて、「clusterにも遊びにおいでよ」と誘うことがあるのですが、そのときによく返ってくるのが、
「今使ってるアバターが気に入ってるけど、VRM化のやり方がよくわからない」という声です。
VRChatはVRMフォーマットを採用していないからこそ起こる障壁ですね。
VRM版アバターが同梱された商品も中にはあるものの、Boothなどで販売されている多くのアバターは、clusterで使うためには自力でVRM化の作業が必要になります。
私も現在使っているアバターはVRM化していますが、正直に言うと、
知識のある方に遠隔で操作してもらいながら「言われるがままポチポチ押した」だけで、工程そのものはほとんど理解できていません。
(いずれこのサイトでも、初心者向けのVRM化の解説記事を出したいなと思っています。)
クラスター社にはぜひ、公式の「VRM化の手順ガイド」などをもっと分かりやすく整備してほしいなあと感じました。
既存ユーザー? 新規ユーザー?
とはいえ、話をひっくり返しますが、これもまた戦略なのでしょうか。
すでにVRChatにどっぷり浸かっているユーザーをclusterに引っ張ってくるより、
「メタバースってなに?」という未経験の人たちに、VRMという共通のフォーマットを紹介して利用してもらうほうが、インフラとしての戦略としては正しいのかもしれません。
実際、clusterのワールドクラフトや簡単なアバター連携機能などは、まさに“ゼロから始める人”に向けた導線として非常に考え抜かれているように感じます。
アトムとは? バーチャルとは?
「アトム」と聞いて、まず鉄腕アトムを思い浮かべる方も多いかもしれません。
ですが、本書のタイトルにある『アトム』とは、物理的な物質そのもの、つまり“現実世界に存在するモノ”=アトム(atom)を意味しています。
そして、それに対比されるのが“情報”や“データ”で構成された存在”=バーチャル”というわけです。
※この記事では詳しい内容には踏み込みませんが、本書では「アトム(物質)からデータ(バーチャル)への移行」について、非常に興味深い解説がなされています。
私自身、「今後の世界はどう変わっていくのか?」という視点で読み進めて、とても刺激を受けました。
「存在しない」は本当に正しい?
「バーチャル」という言葉には、しばしば「仮想」や「存在しないもの」といった意味が込められがちです。
ですが、私はこの「存在しない」「虚構」というイメージには、ずっと違和感を持っていました。
確かに、バーチャルには質量がなく、原子や分子でできているわけではありません。
でも、それをもって「存在していない」と言ってしまうのは、どこか納得がいかないのです。
たとえば、VRで出会った人との思い出。
バーチャル空間で過ごした時間や感情が、「存在しない」と言われるのって、ちょっと乱暴じゃありませんか?
それは「自分自身の存在や過ごした時間は存在しない」みたいな、事実とズレた扱いを受けているような気がするんです。
別に「私を認めてほしい!」とか、そういう気持ちではないのですが、
朝起きて、ご飯を食べて、VR空間で誰かと話して、また寝る──という日々があるのに、それを「存在しない」と言われるのは、ちょっと違う気がするんですよね。
「本物ではないが、本質的に本物」
本書では、「バーチャル=仮想=存在しないもの」という誤解について、明確に否定されています。
そして、“本物ではないかもしれないが、本質的には本物”──そうしたスタンスでバーチャルを定義しています。
この表現、とても良いなと思いました。
バーチャルで「別の存在になれる」という考え方も素敵ですが、
私にとっては「バーチャルで遊ぶ“今の私”も、ちゃんと私自身」なんです。
それを「本物ではないが、本質的には本物」と言ってもらえると、すごく自然に受け入れられました。
こうした「バーチャルとは何か?」という考え方には人それぞれのスタンスがあると思うので、
いつかこのテーマだけでじっくり語ってみたいとも思っています。
「アトムからの移行」は、すでに始まっている?
本書では、「アトム(物質)からデータ(情報)」への移行について語られていますが、
読みながらふと、「もうすでに、私たちはその変化の中にいるのでは?」と思う場面がいくつかありました。
たとえば──
SNSなどで、インフルエンサーが高級ブランドのカフェや飲食店(ディオールやシャネルなど)をレビューする動画を見かけたことはありませんか?
それを見たフォロワーが、「こんな場所、自分ではなかなか行けないから、レビューしてくれて嬉しい!」とコメントする。
このやり取りって、まさに「アトム(実際の体験)」から「レビュー(バーチャルの体験)というデータ」への移行だと思うのです。
体験を“自分で”するのではなく、誰かの体験を“共有”する。
現実に足を運ぶのではなく、データを受け取って満足する感覚が、すでに日常に根付いていると感じます。
逆に、オタク界隈に多い傾向として、
「自分で行って、自分の目で見て、体験してこそ意味がある!」という体験至上主義があります。
私自身、そちらの感覚もよく分かりますし、実際そういう思考で生きてきた部分もあります。
ですが、それとは別の文脈で、すでに多くの人たちが“脱アトム化”の感覚で生活しているのも事実。
つまり、「アトムからデータへ」という流れは、未来の話ではなく、
すでに静かに始まっていて、しかも“普通の暮らし”の中に存在しているんじゃないか──
そんなことを、この本を読みながらふと思いました。
最後に
本の具体的な内容をネタバレせずに紹介しようとすると、どうしても自分の考えや体験談が中心になってしまいますね。
最初はさらっとまとめるつもりだったのですが、語っているうちに気づけばけっこうな文章量になってしまいました。
でも、この投稿を読んで「面白そうだな」「ちょっと読んでみようかな」と思ってもらえたなら嬉しいです。
任天堂が過去に発売した“ちょっと時代を先取りしすぎたVR機器”の話なんかは有名ですが、本書にはそれ以外にも、意外と知られていない他の大手企業のVR機器の話など、メタバースを支えるテクノロジーの歴史や裏話的なトピックも豊富で、知識欲が刺激される一冊でした。
個人的に特に印象深かったのが、
「メタバースでやる意味があることをやろう」というスタンスがはっきり示されていたこと。
私は「インフラを作る」と聞いて、日常生活で行われているような些細な行動――言ってしまえば“地味でつまらないこと”――も、メタバースの中で再現できるようにするのかな?と勝手に想像していました。
でも実際は、「メタバースでは、メタバースでしかできないことをやろうよ!」というメッセージが根底にあって、
それはとてもワクワクする非日常の空間への憧れと理想が込められているように感じました。
この本を読んだことで、私自身のメタバースの見方も少し変わった気がします。
もし気になった方は、クラスター株式会社 代表取締役CEO・加藤直人さんの著書、
『メタバース さよならアトムの時代』ぜひ手に取ってみてください!